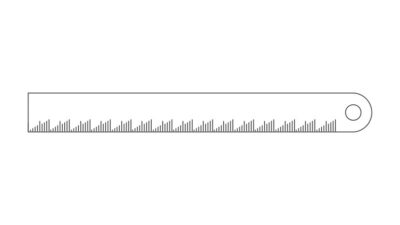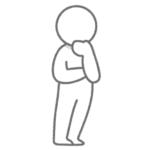
寸法を測定する時によくコンベックスを使うのだけれど、その測定結果を公式なものとしても問題ってないのかな。コンベックスの測定精度ってどれぐらいなのか教えて欲しい。
このような疑問・悩みを持った人へ、お答えしていきます。
機械の設計や製造・組立・検査において、長さを測る測定器具は使用頻度は高いです。
長さを測る測定器具には、ノギスやマイクロメーター、直尺、コンベックス、巻尺などがありますが、なかでもコンベックスは測定範囲が広く、持ち運びもしやすいことから、特に使用頻度が高いです。
そんなコンベックスですが、検査・測定においてコンベックスで測定した値を公式なものとする人をよく見ますが、
そもそも測定をする際は、その測定結果がどれぐらい信頼できるものなのかを知っていて使用する必要があります。
場合によっては、コンベックスだと測定誤差が大きすぎて、使用に適さない場合だってあります。
そこで今回は、コンベックスの測定精度はどの程度なのかについてお話ししていきます。
この記事を読んで、コンベックスの知識を習得し、ものづくりの中でコンベックスをうまく活用できるようになれればいいなと思います。
コンベックスは正式名称「コンベックスルール」といい、JIS B 7512にて規定がされております。
ただ、コンベックスは巻尺の一種であるため、巻尺の場合でも同様の規定が適用されます。
コンベックスはJISで規定されておりますが、「JIS 1級」と「JIS 2級」の2種類の等級があります。
| JIS 1級 | JIS 2級 |
|---|---|
| ±(0.2+0.1L) mm | ±(0.25+0.15L) mm |
ここで許容差の計算には以下のようなルールがあり、これに基づいて計算されます。
具体例で説明いたします。
今、室温が20℃の環境で、あるものの長さを「JIS 1級」のコンベックスで測定したところ「2,890mm」であったとしましょう。
ここから、このコンベックスの許容差を計算します。
まず「2,890 mm = 2.89 m」ですので、許容差の計算式に代入する「L」は、2.89 mから単位「m」を取り除き、さらに1未満の端数を切り上げると、
$$L = 2.89\simeq3$$
よって許容差を計算すると、
$$\begin{align}
許容差&=\pm(0.2+0.1L)\\
&=\pm(0.2+0.1\times3)\\
&=0.5
\end{align}$$
よって、測定結果は「2,890 ± 0.5mm」となります。
許容差ですが、実はいちいち測定値ごとに計算をしなくとも、許容差のパターンは数パターンしかありません。
というのも、市販されているコンベックスは最長でも10mしかないからです。
この許容差のパターンについて、以下のとおりまとめておりますので、ご活用ください。
| 長さ | JIS 1級 | JIS 2級 |
|---|---|---|
| 1 m以下 | ±0.3 mm | ±0.40 mm |
| 1 mを超え 2 m以下 |
±0.4 mm | ±0.55 mm |
| 2 mを超え 3 m以下 |
±0.5 mm | ±0.70 mm |
| 3 mを超え 4 m以下 |
±0.6 mm | ±0.85 mm |
| 4 mを超え 5 m以下 |
±0.7 mm | ±1.00 mm |
| 5 mを超え 6 m以下 |
±0.8 mm | ±1.15 mm |
| 6 mを超え 7 m以下 |
±0.9 mm | ±1.30 mm |
| 7 mを超え 8 m以下 |
±1.0 mm | ±1.45 mm |
| 8 mを超え 9 m以下 |
±1.1 mm | ±1.60 mm |
| 9 mを超え 10 m以下 |
±1.2 mm | ±1.75 mm |
コンベックスの目盛の部分については、真直度の規定があります。
真直度とは、理想的に真っ直ぐな(幾何学的に正しい)直線に対して、対象となる線がどれだけ真っ直ぐになっているかを表します。例えば「真直度0.1」であるということは、「間隔が0.1mmとなるように平行に引かれた理想的に真っ直ぐな2本の直線の間に、対象とする直線が収まっている」という意味になります。
わかりやすくいうと、真直度が悪いコンベックスは、目盛の部分がふにゃふにゃ曲がっていたり、ガタガタになっていたりしていることを意味します。
コンベックスが規定されている真直度は、コンベックスのテープの材質によって異なり、以下のとおりとなります。
| 呼び寸法 | 鋼製の真直度 | ステンレス鋼製の真直度 |
|---|---|---|
| 3 m以下 | 呼び寸法の1/500以下 | 呼び寸法の1/500以下 |
| 3 mを超え 5 m以下 |
呼び寸法について6 mm以下 | 呼び寸法について6 mm以下 |
| 5 mを超えるもの | 任意の5 mについて6 mm以下 | 任意の5 mについて10 mm以下 |
ちょっとわかりづらいので解説しますと、
「呼び寸法の1/500以下」というのは、例えば1 mであれば、「1,000 mm × 1/500 = 2 mm」なので、2 mm以下という意味になります。
「呼び寸法について6mm以下」というのは、例えば4 mであれば「4 mテープを出したときのテープの真直度が6 mm以下」という意味になります。
「任意の5 mについて6 mm以下」というのは、例えば7 mであれば「7 mの中で適当に5 mの長さ分をとって、その真直度が6 mm以下」という意味になります。
これはコンベックス特有の規定ですが、JISではテープ幅が13mm以上のコンベックスルールは、検査台の一端から凹面を上にして長さD(Dはテープ幅の50倍以上)だけ引き出した時に、自重でテープが折れ曲がってはならない」と規定されております。
つまり、コンベックスを製造する際は、水平方向にテープを出した時に、この長さをクリアできるようなテープの剛性を確保しなければならないのです。
市販されているテープ長さ13mm以上のコンベックスは6種類あり、それぞれについて計算すると以下のようになります。
| テープ幅 &91;mm&93; | 自重で折れないテープの最小長さ &91;mm&93; |
|---|---|
| 13 | 650 |
| 16 | 800 |
| 19 | 950 |
| 22 | 1,100 |
| 25 | 1,250 |
| 27 | 1,350 |
今回のポイントをまとめると、以下のとおりとなります。
なお、おすすめのコンベックスについては、こちらの記事をご覧いただければと思います。
また、直尺(スケール)の精度について知りたい人はこちらの記事をご覧ください。
今回は以上となります。ご一読、ありがとうございました。
ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。
ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり
機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。
構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...


おすすめのコンベックス【いろいろな機能があります】
目盛が見やすい測定器:快段目盛の魅力【おすすめ】